

この記事ではこんな知識を紹介しています。
- 鏡開きが遅れると縁起が悪い?
- 鏡餅はいつまで飾る?
- 鏡餅のおいしい食べ方
鏡餅を飾ったはいいけれど、気がつくとずっと飾りっぱなしになっていませんか?
毎年のように鏡開きが遅れたりしていませんか?
正確にいつからいつまで飾るの正しいのか、ちゃんと知っている人は少ないでしょう。
なんとこれ、関東と関西では時期が違うんですよ!
そこで今回はお正月のお飾りとして最もポピュラーな鏡餅に焦点を当てて、鏡餅はいつから飾っていつ下げれば良いのか、さらに鏡餅を下げた後の美味しい頂き方などをご紹介します。
鏡開きが遅れると縁起が悪い?
鏡餅を下げる日を「鏡開き」と言います。
この鏡開きが遅れたからといって縁起が悪いわけではありません。
どうしても用があって出来ない、急な用事でできなかった場合、何日にずらすといいのかというと、特別決まりもありません。
鏡開きはもともとは武家の習慣であり、占い的な要素もありました。
それを一般の庶民が真似て行うようになったので、その中身についてはわりとアバウトなのかもしれませんね。
鏡餅はいつまで飾る?【関東&関西】
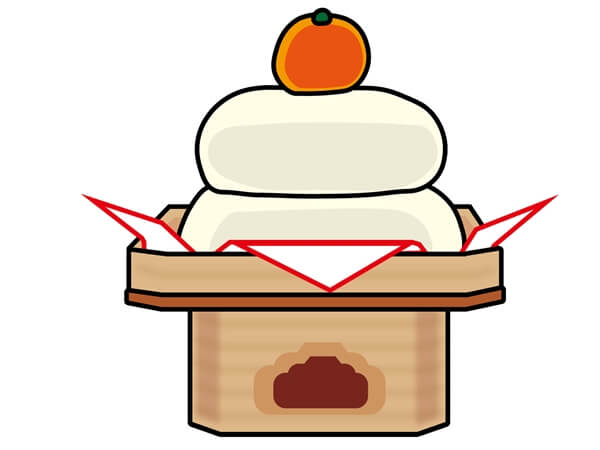
鏡餅をいつまで飾るかというと、関東と関西では微妙に「下げる日付」が違います。
- 関東の鏡餅を下げる日は1月11日(毎年同じ日)
- 関西の鏡餅を下げる日は1月15日(こちらも毎年同じ日)
京都だけ特別に早くて1月4日が下げる日です。
関西以外の日本のほとんどの地域では、1月11日が常識。
多くの地域でなぜ1月11日に鏡餅を下げるかと言うと「1」がそろう日だから。
1が3つも揃う「ぞろ目の日にち」で、縁起が良いと昔の人は考えたのでこの日になったそうです。
ただ、地方によってもいろいろな考え方があり、普通は一夜飾りだと避けられる31日から飾る地方もあるんですよ。
⇒鏡開きの日付が関東や関西など各地で微妙に違う理由はこちらの記事をご覧ください。
いつからいつまで飾るのが常識?
全国的には鏡餅をいつからいつまで飾るかというと、12月28日から1月11日までが通常の期間です。
12月28日の「8」が末広がりの縁起のよい数字のため、12月28日に飾る習慣になったと言われています。
12月29日になると日付に「9」がついて「苦しむ」を連想するため避けられます。
また31日に飾ると「一夜飾り」と言われ、お家に来てくれる神様に失礼とされるのでなるべく避けましょう。
1月15日の小正月を目安に
もし1月11日に鏡餅を下げられなかったら(鏡割りができなかったら)、1月15日の小正月が適していると思います。
この小正月は「どんど焼き」というお正月の飾り物と一緒に餅を焼いて食べるという行事の日。
小正月をもって「お正月が終わる」という区切りの日でもあるので、もし別の日にずらすとしたら、ぴったりの日と言えます。
鏡餅はどうやって食べるのが美味しい?
鏡開きしたお餅の食べ方ですが、パックのお餅ならお好きな調理方法で美味しく頂けます。
大きなお餅でできた鏡餅はかっちかちになっていますので
- 煮込んで食べる「おぜんざい」
- お雑煮
などひと手間かけると美味しく食べることができますよ。
七草粥に入れるのもいいアイディアです。
カッチカチに固い鏡餅は、電子レンジで少しずつ加熱して柔らかくすると細かく分けるのが楽になります。
温めすぎてベチャッとならないように気をつけてください。
こちらは本当にカチカチなガラスで作る鏡餅(笑)
まとめ
鏡開きや鏡餅の常識をお伝えしてきました。
要点をまとめると
- 鏡開きが遅れても別にかまわない
- 鏡餅を下げる日は関東などほとんどの地域では1月11日
- 関西では1月15日で、京都だけは1月4日
- 鏡開きの日をずらすなら小正月にする
- 家族みんなで神様に感謝しながら頂く(調理のおすすめはおぜんざいやお雑煮)
このようになります。
お正月のお飾りには色々な種類があります。
門松、しめ縄、神棚も用意するお家もありますが、一番手に入れやすく親しみのあるお飾りと言えば鏡餅ですよね?
この鏡餅は簡易なものや小さいものはスーパーでも安く買えるので、これだけは毎年欠かさないという家庭も多いはず。
鏡餅は一番身近なお飾りだからこそ,きちんと飾りたいですよね~
これで来年はばっちり神様を迎えることができそうです。

コメント