春の到来を告げる味覚のひとつ「たけのこ」。
たけのこ掘り(狩り)は、食べる楽しみだけでなく、探す楽しみや掘り出した際の達成感も味わえるのが魅力ですよね。

でも毎年、行こうかどうしようか?迷っているうちにシーズンが終わってしまいます……
そこで遅れを取らないように
- たけのこ掘りの服装・持ち物
- 最適な時期や季節
についてパパっと解説します。
それを頭に入れて、絶好の時期を逃さないようにお出かけください。
これで完璧!たけのこ掘りの服装・格好

たけのこ掘りに行くときに適した服装(格好)がこちらです。
【たけのこ狩りの服装】
- 動きやすく汚れてもいい服(長袖・長ズボン)
- 頑丈で滑りにくい靴(長靴・スニーカー)
- 帽子
- リュックサック
装備は本気モードで!
たけのこ掘りは山の中に入って行うため、数ある「狩りもの」の中でもハードな部類。

ヒール靴や短パンなどでは行かず、きちんと装備して臨みましょう。
また、春先は冬眠から目覚めたばかりの蛇に遭遇しやすい時期でもあります。
笹の葉でケガをする恐れもあるので肌の露出は控えてください。
かがんだりしゃがんだりする事も多いので、ストレッチがきいたズボンがおすすめです。
また、たけのこが生えている場所は斜面であることも多いので、足元は丈夫で滑りにくい靴にしましょう。
スニーカーよりもできれば農作業用の長靴があると、汚れてもいいし転びにくいので向いていますよ。
また、大き目のリュックがあれば、収穫したたけのこを持ち帰るのに便利です。
忘れ物厳禁!たけのこ掘りに必要な道具リスト
続いて、たけのこ掘りに行く時に持っていく道具のリストです。
【たけのこ狩りの持ち物】
- 鍬(くわ)または大き目のスコップ
- 軍手
- 新聞紙
道具を貸してくれる農園もあるようですが、こだわりたい方はマイ鍬を買ってもよいかも知れません。
たけのこ掘り専用の鍬を使うと効率がグンと上がり、労力も激減しますよ。
【タケノコ掘りや山菜採り専用のスコップ】
使う鍬は地域によっても違うと言います。
うーん、たけのこ狩りの世界は意外と奥深そうです(笑)
新聞紙は、たけのこを持ち帰る際に使います。
ビニール袋にむきだしでバサッと入れるよりも、ひとつずつ包むだけで鮮度に違いがでますよ。
【安全対策】熊よけに必要な意外な道具
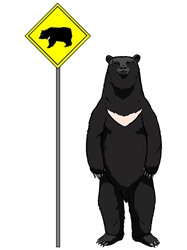
近年、たけのこ掘りで熊に襲われ死傷者がでる被害が相次いでいるのをご存じですか?
そこで、熊よけに効果があると言われる道具を必ず持参しましょう。
【熊よけ効果のある道具】
- 笛
- 爆竹
- ラジオ
- 鈴
熊は本来、自ら人間に近づいてくることはないと言います。
ですから、鈴にしてもラジオにしても「音を鳴らすこと」で人間の存在を熊に知らせることが目的です。
しかし、終始鳴り続けるその音が、かえって近づく熊の足音や気配をかき消してしまう側面も……。
ただでさえ、たけのこ掘りをしている人は下ばかり見ているので危険を察知しづらいと言われるので注意が必要です。
笛や爆竹は、適宜鳴らせるのが利点ですね。
そして、意外と効果的なのが人の声。
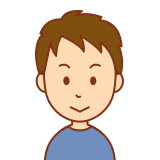
おーーーーい!(大声)
と叫んだりするのはもちろん、人の話し声だけでも違うといいますよ。
しかし、2016年に秋田で起きたクマによる死亡事故では、鈴が人慣れしたクマをおびき寄せた可能性があると言われています。
こうなってくると一体どうしたらいいの…という気もしますが
熊が出る山には入らない
この一言に尽きます。
熊の出没情報は、市町村のHPにも記載されていますから事前に確認して下さいね。
まあ、観光農園でのたけのこ狩りならこのような心配はないと思いますが。
たけのこ掘り(狩り)に最適な時期や季節

たけのこ掘りに行くのに最適な季節は言うまでもなく「春」です。
ただ一口に春と言っても縦に細長い日本列島ですから、東北や四国地方はもちろん、関東や関西など各地域によって微妙に時期が異なります。
こちらに日本各地のベストシーズンをまとめました。
【日本各地の竹の子掘りベストシーズン】
- 九州地方…3月中旬~4月下旬
- 中国/四国地方…4月上旬~5月上旬
- 関西地方…4月上旬~5月上旬
- 関東地方…4月上旬~5月上旬
- 東北地方…4月下旬~5月下旬
上記は、最もポピュラーなたけのこ「孟宗竹(もうそうちく)」の収穫最盛期です。
種類が違えば旬も異なりますし、成育状況により変動しますのでご注意くださいね。
たけのこ前線をチェック
たけのこ掘りのおおよその目安は4月ですが、実はもっとわかりやすく旬を知る方法があります。

それが桜前線ならぬ、「たけのこ前線」です。
桜前線が通過した1週間~10日後ぐらいが、その地域のたけのこのピークという訳です。
たけのこ前線は、3月に鹿児島から始まって本州を北上し続けます。
桜前線はニュースでも取り上げられますから、意識しやすいですよね。
たけのこは成長がとても早く、10日位(旬日)で竹に成長していまうことから「筍」という字が生まれたと言われます。
時期が近づいたら、目的のたけのこ農園や観光協会の情報をチェックして、タイミングを逃さないようにして下さいね!

あっという間に竹になっちゃいますから。
【たけのこ掘り名人によるお手本です】
まわりの土を掘っていく感じですね。
まとめ
私が子供の頃は、たけのこが生えている山が近所にたくさん残っていました。
たくさんお裾分けしてもらい、母がコトコトあく抜きをしていたのを覚えています。
家中に米ぬかの香りが広がって、いまでもその匂いを嗅ぐと子供時代の新学期を思い出します。
昔から「たけのこを掘り始めたら、お湯をわかしておけ」と言われます。
それぐらい、手早くあく抜きをするのが大事ということです。
※たけのこの簡単なアク抜き方法については、別記事をご覧ください。
たけのこ掘りは重労働ですが、あく抜きをする余力はぜひ残しておいてくださいね(笑)

コメント