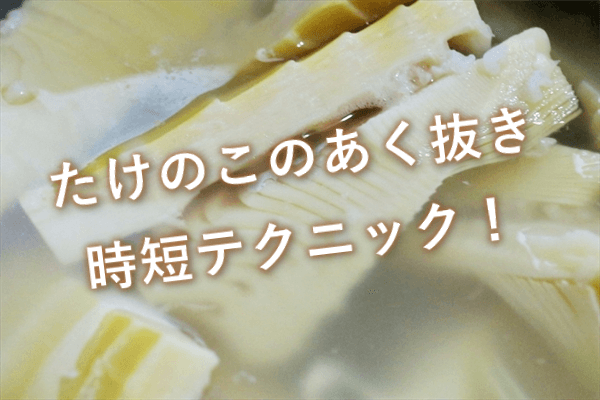
春を感じる味覚の代表格「たけのこ」。生の筍を味わえるのは、年間を通してこの時期だけです。
おいしいタケノコですが、食べるまでが大変で
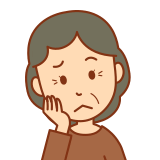
あく抜きが面倒なのよ~~~
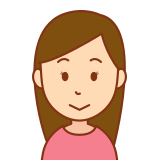
そもそもやり方が分からなくて……
といった声もよく聞きます。

はい、以前の私もそのひとりでした(笑)
でもこの裏技(時短テクニック)を知った今では、たけのこのあく抜きなんて朝飯前です。
そこで「苦手だよ~」とお嘆きの方に、私が実践している
- 「ある道具」で15分で筍のアク抜きをするテクニック
- 「ある野菜」で1時間放置するだけでアク抜きをする裏技
こんな賢い方法を大公開しちゃいます。
たけのこのあく抜き時短テクニック!15分で完了!

私の一番のオススメは圧力鍋を使ったあく抜きです。
普通の鍋を使ってあく抜きをする場合、ゆで時間だけで約1~2時間。
その後、お湯が常温になるまで冷ます必要があるため一晩かかることもあるほど。
それが、圧力鍋を使えば加熱時間は15分程度!
では、早速その手順を具体的に見てみましょう。
圧力鍋を使った灰汁抜きのやりかた
用意するものはたったこの2つだけ。
- 米のとぎ汁
- 圧力鍋
やり方の手順がこちらです。
1.圧力鍋に皮を剥いた筍を入れて、被るぐらいの米のとぎ汁を入れます。
※米のとぎ汁は、とぎ始めの濃い部分を使ってください。
2. 圧力をかけて「重り」があがったら弱火で15~20分加熱し、その後は冷めるまで放置します。
3. 冷めた筍はきれいな水につけて冷蔵庫で保存します。
このあとは毎日水をかえれば約1週間はもちます。
また、米のとぎ汁の代わりに「水+重曹」でもOK!
その場合は、水1リットルに対して小さじ1を目安にしましょう。

圧力鍋をお持ちの方は、是非試してみてください。
【とぎ汁ではなく「お米の粒」を入れるやり方もあります】
【圧力鍋がない場合】筍のアク抜きを時短で済ます裏技
もちろん、ご家庭に圧力鍋がない方も多いと思います。
そんな方におすすめしたい方法が「大根のしぼり汁」を使ったあく抜きです。
大根の絞り汁をつかった灰汁抜きのやりかた
手順は以下のとおりです。
1. 大根のしぼり汁200cc(約1/3本分)に同量の水と全体量の1%の塩を加えます。
2. 1に皮を剥いて薄切りにした筍を1~2時間漬けます。
3. これで大方のあくは抜けていますが、念のため調理前に1~2分茹でます。
筍ご飯などは、あく抜き後に下茹でせずにそのまま調理しても大丈夫です。
この方法が簡単なのは、何といっても漬けるだけでいいこと。
最大の難関は大根をおろすことでしょうか。
大根は皮つきのままで構いませんが、なるべく細かくおろすのがおすすめです。

フードプロセッサー等を使って手間を省けば、時間短縮がはかれそうですね。
ゆで時間がほとんどないため、光熱費を節約できるのも嬉しい限りです。
今回は短時間であく抜きができる方法をご紹介しましたが、筍はゆですぎたからといって溶けたり煮崩れたりすることはありません。
しっかりあく抜きしたいのなら、できるだけ長い時間ゆでてくださいね。
どれが一番早い?所要時間を比較
タケノコのあく抜きの方法は様々ありますが、どれが一番早いのでしょうか?
ここまでご紹介してきた方法の所要時間を比べてみます。
■米ぬか(所要時間120分)
皮がついたままの筍を米ぬか・唐辛子と一緒に柔らかくなるまで煮る方法です。
米ぬかに含まれるカルシウムが筍のえぐみの原因であるシュウ酸に作用し、えぐみを感じさせなくします。
また、米ぬかの脂肪分やアミノ酸が筍を柔らかくし旨さを引き出します。
筍を煮るのに1時間以上、その後湯が常温になるまで1時間以上かけて冷まします。
■米のとぎ汁(所要時間120分)
米ぬかがない場合は、米のとぎ汁でも代用可能です。
とぎ始めの濃いとぎ汁がおすすめです。
また、大きい筍はあくが強いので少量の生米を足します。
この場合も、米ぬか同様1時間以上煮て、その後お湯が常温になるまで冷まします。
■重曹(所要時間60分)
皮を剥いた筍の先端を切り落とし、水1リットルに対して3グラムの重曹を入れて火にかけます。
柔らかく煮るまでの所要時間は米ぬかと同じですが、荒熱を冷ます工程がない分早く終わります。
ゆで終わったら、流水で洗ったあとすぐに調理可能です。
■大根のしぼり汁(所要時間60分~120分)
大根のしぼり汁200cc(約1/3本分)に同量の水と全体量の1%の塩を加え、皮を剥いて薄切りにした筍をつけます。
約1~2時間漬けるだけで大方のあくは抜けますが、調理前に1~2分茹でます。
■圧力鍋(所要時間15分~)
圧力鍋を使う際も、米のとぎ汁または重曹を使います。なお、米ぬかは圧力鍋のふたの部分に詰まる恐れがあるのでご注意ください。
たけのこの大きさにもよりますが、15~20分で茹であがります。
出来上がった筍は、お湯が冷めるまで漬けておきます。
・・・と、こうして比較してみると、やっぱり圧力鍋+米のとぎ汁が一番時間がかからないことがわかりますね。

圧力鍋も安いものは5,000円ほどで買えますよ。
面倒なタケノコのあく抜きはなぜ必要?
そもそも、なぜ筍はあく抜きをする必要があるのでしょうか。
実は、朝収穫したての筍は、そのままでも美味しく食べることができます。
しかし、時間が経つにつれ「えぐみ」が増して筍特有の香りがなくなり、1日経つと2~3倍にも「えぐみ」が増えると言われています。
つまり、なるべく早くあく抜きをすることが、美味しく頂くための秘訣と言えるわけです。
そして、このえぐみの原因となるのが
- シュウ酸
- ホモゲンチジン酸
という2つの成分。
米ぬかにはカルシウムが含まれており、一緒に調理することでシュウ酸に作用し、えぐみを感じさせなくします。
また、共にえぐみ成分であるホモゲンチジン酸は、重曹や米ぬかなどアルカリ性の水で調理することで取り除くことができます。
米ぬかや重曹があく抜きに使われるのは、ちゃんとした理由があるんですね。
まとめ
たけのこのアク抜きを時短で済ますテクニックをご紹介してきました。
あらためて要点をまとめると
- 圧力鍋で米の研ぎ汁で煮れば15分で完了
- 重曹で煮ると60分で完了
- 大根のとぎ汁なら煮ないで放置して2時間で完了
もっとも時短なのが圧力鍋を使う方法。
お持ちでない場合は重曹で煮るか、大根のとぎ汁に漬けて放置する方法がおすすめです。
以前、友人から皮つきの筍をもらった時のこと。
時間がなくて数日放置していたら、「えぐみ」が抜けない不味い筍になってしまった経験があります。
以来、筍には苦手意識があり買うのはもっぱら水煮ばかり。
でも母からこの「あく抜きを短時間で済ます裏技」を教わったことで筍がぐっと身近になりました。
みなさんもぜひこの春こそ、生の筍を買って旬な筍料理を食卓に並べてみてくださいね♪

コメント