

この記事では小学生でも覚えられる暗記法をご紹介します。
- 春の七草を語呂合わせで覚える方法
- 春の七草をリズムで覚える方法
七草粥に入れる春の七草って、大人になっても覚えている人って少ないですよね?
七草というのですから、もちろん7種類の草花の名前があるのですが・・・この草の名前、すべて言うのって難しい!
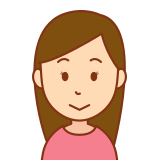
覚えていなくても日常生活に特に問題ないわ。
と言う人もいます。
でも日本人の教養として、ふとしたときに説明できるとステキではありませんか?
今回はこの春の七草を三分で完璧に覚えられる「リズムに乗せる」・「語呂合わせ」の暗記方法をご紹介します。
あっ、ちなみにこの春の七草、秋の七草と並んで中学受験で種類を書く問題が出題されることもあるそうです。
これは小学生のお子さんを持つ親御さんも必見ですね!
【小学生でも可】春の七草の覚え方(語呂合わせ&リズム)
春の七草って呪文みたいな言葉が並んでいて、なかなか暗記するのは難しいですよね?
でも、簡単な覚え方があるんです。それが
- 語呂合わせにする
- 短歌にリズムに合わせる
という2つの方法。
では、それぞれの覚え方をくわしく説明していきましょう。
【その1】語呂合わせで暗記

短歌はちょっと苦手で…といわれる方は頭文字の語呂合わせで覚えるなんていかがでしょうか?
覚えるフレーズは「セナはゴッホとすず2つが好き」。
このフレーズは春の七草の「頭文字」を抜き出して、ひとつの文章にしたもの。
(ナ)⇒なずな
(は)⇒はこべら
(ゴ)⇒ごぎょう
ッ
(ホ)⇒ほとけのざ
と
(すず)⇒すずな・すずしろ
2つが好き
このフレーズを何度も何度も復唱してみましょう。

強引な語呂合わせなので意味不明ですが、この言葉一度聞くと忘れませんね(笑)
セナもゴッホも七草には関係ありませんけど、覚えやすいかもしれません!
突っ込みどころ満載の面白い語呂合わせで楽しく覚えられそうですね。
もうひとつ別の語呂合わせも!
某有名中学受験塾の講師は、このような語呂合わせを推奨しています。
覚えるフレーズは「せなはごほすーすー」。
セナくんというキャラクターが風邪をひいてゴホゴホと咳をして、すーすーと寒がっている様子をイメージする方法です。
こちらも覚えやすくていいかもしれません。
【その2】短歌のリズムに合わせて暗記♪
私の一番のおすすめの覚え方は、短歌のリズムに乗せて暗記するやり方。
百人一首を読み上げるトーンで春の七草を順番に読み上げると、リズムに合わせて覚えやすいですよ。
【覚え方:百人一首のリズムで何度も読み上げる】
その短歌がこちらの
「秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ」
という句。(百人一首の第一首目の短歌)
この句を平仮名にすると
「あきのたの・かりほのいおの・とまをあらみ・わがころもでは・つゆにぬれつつ」
になります。
この句の言葉の切れ目に、それぞれ春の七草の「草」の名前を当てはめて読み上げる練習をしてみましょう。
対応する語句がこのようになります。
- あきのたの⇒せり・なずな
- かりほのいおの とまをあらみ⇒ごぎょう・はこべら・ほとけのざ
- わがころもでは⇒すずな・すずしろ
- つゆにぬれつつ⇒はるのななくさ
何度か繰り返し口ずさんでいると、いつの間にか覚えられます。
次思い出すときも唄うように「すらすらっ」とでてくるので気持ちいいですよ〜。
春の七草の特徴
春の七草は1月の上旬にお粥にして食べる習慣があります。
この習慣は、年末年始にごちそうをたくさん食べて負担をかけてしまった胃腸に「優しいもの」を食べて疲れを癒やすのが目的のひとつ。
ですので、春の七草はそれぞれ体に優しい効果が期待できるんですよ。
■せり
ビタミンCやミネラルが豊富で食欲増進に効果があります。
せり特有のさわやかな芳香には鎮静効果もあります。
■なずな
栄養価の高さから古くから薬草として使われてきた万能食材。
肝臓病をはじめ、高血圧や生理不順などに効果があります。
■ごぎょう
咳止め効果もあり、風邪予防に効果的。
舌触りがあまりよく無いため、普段は食用にはしない食材です。
■ほとけのざ
解熱、鎮痛作用があり、歯痛止めにも使われてきたそうです。
■すずな
かぶの別名。
葉にはカルシウム、鉄分等多く含み、ビタミンが豊富。
根の部分はでんぷん分解酵素を多く含み便秘改善に役立ちます。
■すずしろ
大根の別名。
葉にはビタミンたっぷりで風邪予防に効果的。
根の部分はジアスターゼという酵素が含まれていて消化を助けます。
■はこべら
利尿・歯痛・消炎効果があります。
汁で歯を磨くと歯にも良いそうです。
まとめ
春の七草の覚え方は
- リズムに乗せる方法
- 語呂合わせ
の2種類あります。
あなたの覚えやすい覚え方でマスターしてくださいね!
余力があれば、それぞれの栄養価も覚えていれば普段の食生活ももっと豊かになりますよ〜。

コメント