
「お粥」と聞くと、風邪をひいたときや胃腸が弱っているときに登場するイメージがありませんか?
しかし、小豆粥は別で特定の日(時期)にだけ食べるものです。
そこで今回は
- 小豆粥はいつ食べるのか?
- 小豆粥の由来
- 動画で分かる作り方
をご紹介します
小豆粥はいつ食べる?
結論から言うと、小豆粥を食べるのは1月15日です。
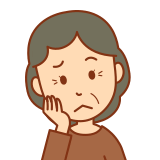
えっ?、1月15日?我が家は他の日に食べていたわ!
という方もいらっしゃるはず…。
そうなのです。
地域によっては12月の「冬至」に小豆粥を食べるところもあります。
しかし、ほとんどの地域で小豆粥は、1月15日、または「冬至」にいただくのが今では一般的なんですよ。
小豆粥を食べる由来とは?
古来、中国では冬至に「小豆粥」を、1月15日には「豆粥」を食べていて、その習慣が日本に伝わってきました。
1月15日は、小正月(女正月)ともいわれ、正月中に一生懸命動いていた女性を休ませる意味合いも持っています。
その小正月の代表的な食べ物が、小豆粥です。
小豆は赤い色をしていますよね!
この赤い色が厄を払うと考えられてきたため、邪気を払い健康を祈願する意味合いをこめて食すようになりました。
小豆の入っているお赤飯でもお分かりのように、小豆は縁起の良いものとしてハレの日に出てくることが多いのです。
【簡単レシピ】小豆粥を作ってみよう!
こちらの動画は、小豆の水煮缶詰を使っているので、簡単に作ることができます!
一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
【材料:二人分】
- 米→45g
- 小豆水煮の缶詰→30g
- 小豆水煮の缶詰の汁→1/2カップ 100g
- 水→2カップ
- 塩→少々
【作り方】
1.洗ったお米、小豆、缶詰の汁、分量の水を鍋に入れる。
2.蓋をして強火にかける。
3.ひと煮立ちしたら蓋を少しずらす。
4.ふきこぼれないように火を弱めて、30分ほど炊く。
5.炊き上がったら火を止めて蓋をする。
6.5分ほど蒸らして、全体をさっと混ぜる。
7.器に盛って、塩をふったら、できあがり
小豆の種類はたくさんある!
小豆と一言に言っても、実はたくさんの種類があることをご存知でしたか?
大納言という種類を聞いたり見たりすることもありますが、これは普通の小豆とは区別されています。
大納言は、大粒、そして皮が破れにくい、煮崩れしにくいという利点があります。
一般的に、それ以外の品種を小豆と呼んでいます。
産地や品種、栽培方法など調べながら、小豆を楽しむのもおもしろいかもしれませんね。
まとめ
健康や美容のために食べている方もいらっしゃる小豆。
日本人の私たちにとって、小さなときから身近にある食べ物の1つではないでしょうか?
あんぱんやおはぎ、あんこ餅など小豆が使われているものをあげればきりがありません。
ここまで書いておきながらなんですが…実は私…小豆が大の苦手です…。
でも、家族は小豆が大・大・大好きなんです!!
正直…苦手な小豆についてこんなに調べる日がくるとは…思ってもいませんでした(笑)
でも、家族の大好物をおいしく調理して食卓へ並べられるのは、楽しみの一つでもあります。
しかも今回は小豆粥を食べる意味まで、伝えることができます。
そして、小豆にたくさんの種類があることも判明。
産地や品種で、私でも食べられるものと出会えるかもしれません。
そう考えるとわくわくします。
1月15日は、家族で小豆粥を囲みながら、1年の健康を願いたいと思います。

コメント