茅の輪くぐりの「正しいくぐり方」をご存知でしょうか?
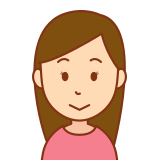
正しい作法や意味も知らずテキトウにやってるけど?
という方がほとんどではないかと。
そもそも「茅の輪潜りって一体何?」と思う方もいますよね。
そこで今回は
- 茅の輪くぐりの正しいやり方
- 茅の輪くぐりの意味と由来
- 茅の輪くぐりができる神社一覧
などをまとめてみました。
恥をかかないように是非参考にしてくださいね。
恥をかかない!正しい茅の輪くぐりの作法とやり方

正しい茅の輪くぐりの作法がこちらです。
全部で4ステップに分かれますので間違えないように予習しておきましょう。
1. 茅の輪の前に立って軽く礼をします。そして左足から輪をくぐり、左回りに回って、元の位置に戻ります。
2. 茅の輪の前に立って軽く礼をします。そして右足から輪をくぐり、右回りに回って、元の位置に戻ります。
3. 茅の輪の前に立って軽く礼をします。そして左足から輪をくぐり、左回りに回って、元の位置に戻ります。
4. 茅の輪の前に立って軽く礼をします。そして左足から輪をくぐり、ご神前まで進み、「二拝二拍手一拝」の作法でお参りします。
【茅の輪くぐりのレクチャー動画です。コレどおりにやれば完璧!】
神拝詞を唱えながらくぐる
神拝詞とは「しんぱいし」、または「しんぱいじ」と読みます。
茅の輪をくぐりをするときは、この神拝詞を唱えながら行います。
「はらへたまへ きよめたまへ まもりたまへ さきはえたまへ」
茅の輪くぐりの意味
そもそも茅の輪は「神具のひとつ」と考えられています。
茅の輪くぐりをすることで
- 半年間の罪や穢れを落とす
- 残りの半年間の無病息災を祈願する
という意味があります。
茅の輪くぐりの由来

茅の輪くぐりの由来は「日本神話」からきています。
素戔嗚尊(スサノオノミコト)が南海の神の娘と結婚するため、南海の旅路の途中に
- 蘇民将来(そみんしょうらい)/兄
- 巨旦将来(こたんしょうらい)/弟
という兄弟のもとを訪ねて「泊めてほしい!」と嘆願しました。
しかし弟の巨旦将来は裕福なのに宿泊を受け入れず、兄の蘇民将来は貧しかったものの喜んで宿泊を受け入れました。
それから数年後、素戔嗚尊(スサノオノミコト)が蘇民将来のもとを訪ねて
「悪い病気が流行れば茅の輪を作り、腰につけなさい」
と教えました。
その後、病気が流行り巨旦将来は病気で倒れましたが、その教えを守ったおかげで蘇民将来は無事に助かりました。
これが茅の輪くぐりの由来とされています。
昔は茅の輪を腰にぶらさげていましたが、江戸時代に「茅の輪をくぐって災いを取り除く」という現在の形に変化しました。
夏越の祓2022年の日程@どんな行事か3分で分かる解説付き
茅の輪くぐりが体験できる全国の神社一覧

実際に茅の輪くぐりができる有名な神社をご紹介していきます。
【東京都】
・浅草神社
・日枝神社
・湯島天満宮
・明治神宮
・上賀茂神社
【神奈川県】
・寒川神社
【埼玉県】
・氷川神社
【奈良県】
・大神神社
【大阪府】
・大阪天満宮
【京都府】
・下鴨神社
・吉田神社
まとめ
茅の輪くぐりについて理解が深まったでしょうか。
実は私、今回調べてみるまで「茅の輪くぐり」を「かやのわくぐり」と読んでいました。
知り合いに茅野(かやの)さんという人がいるので、それでついついそう読んでしまいます・・・・。
でもあらためて調べてみて、日本らしい伝統のある素晴らしい行事だと思いました。
潜り方などの作法をしっかり覚えてやってみてください。
ただ、縁起がいいからといって茅の輪を持って帰るのはやめましょう。
実はこの茅には潜った人の罪や穢れが移って逆に悪い厄のようなものを連れ帰ることになってしまうらしいです。
小さいころに訳も分からず茅の輪を持って帰ろうとして親にこっぴどく怒られた経験があります。

コメント
『茅の輪』と『芽の輪』併用して説明してるけど同じなの?『茅の輪』は知ってるけど『芽の輪』は初めて知りました。
気づかずに誤った字を使っていたようです。
すべて修正しました。
ご指摘ありがとうございます。
修正したと書いてますが、芽の輪と何回も出ています。
公に情報を出しているサイトならしっかりと書いていただきたいものです。
見た目が似ている字のため、まったく気が付きませんでした。
わざわざご指摘くださって、ありがとうございます。