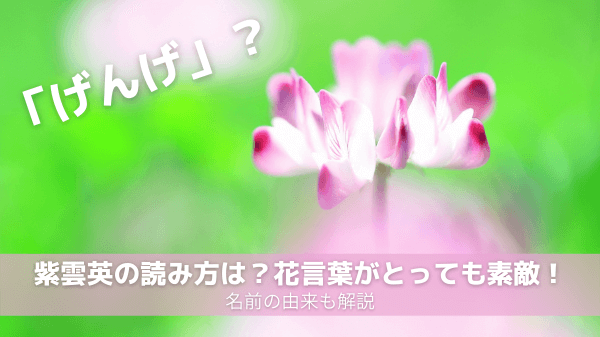
道端に咲いていた「紫雲英」の花。
その時は名前も知らずにただ「綺麗だな」と思って眺めたり、ちぎって花飾りにして遊んだりしていました。
それにしてもこの花の名前、難しいですね。読めますか?
わざわざ漢字で書いたのには理由があるんです。
だって、花の名前(漢字)が、その容姿をぴったり表現されていて、とても素敵だったものですから。
さらには、花言葉までこの花らしい素敵なものでした。
ここでは、そんな
- 紫雲英の読み方
- 紫雲英の花言葉
- 紫雲英の名前の由来
などなど、花にはちょっと詳しい私がご紹介します。

読み終わるころには、きっと今より春が待ち遠しくなりますよ♪
「紫雲英」の正しい読み方

この「紫雲英」という花の読み方は、ずばり「げんげ」です。
私、一番初めにこの読み方を見た時に見返しました。

え?ほんとうに?
って、びっくりしちゃって。
なんだか、イメージと違ったんです。みなさんはどうですか?
さらに調べますと、漢字そのままに「シウンエイ」と呼んでもOKなんですね。
わたしはこっちの読み方の方がしっくりきたんですが、別名のことを知ってなるほどと思いました。
こっちの方が有名?紫雲英の別名
「紫雲英」には皆さんおなじみのもうひとつの別名があります。

それが「レンゲソウ」・「レンゲ」なんですね。
「レンゲソウ」は漢字で書くと「蓮華草」で、「レンゲ」は「蓮華」と書きますが、「紫雲英」を含めてすべて同じ花の名前です。
紫雲英の「げんげ」という呼び方は「れんげ」が訛ってそう呼ばれるようになったともいわれています。
なぜこんな風に2つも呼び名があるかというと
- 蓮華草が「和名」
- 紫雲英が「漢名」(こちらが正式名称)
と、中国での呼び名(漢名)と日本での呼び名(和名)があるからなんですね。
みなさんはどちらの名前でご存知でしたか?
一般的には「蓮華草」という名前の方が知れわたっているのではないでしょうか。
でも「紫雲英」という呼び方を知ることによって、そちらの名前も花の様子を良く表していると感心しました。
さて、それらも踏まえて、お待ちかねの名前の由来をご紹介しますね。
「紫雲英」・「蓮華」という名前の由来は?

二つの名前それぞれに由来があるので、わけてご説明しますね。
紫雲英の名前の由来
紫雲英は「緑肥」といって、畑や田んぼの肥料になります。
なので、日本では昔から田んぼ一面に紫雲英を植えることが多かったそうです。
その薄紫の花が田んぼ一面に咲き乱れる様子が、遠くから見るとまるで紫色の雲が低いところで漂っているように見えたところから、「紫雲英」と名付けられました。
私もこの光景を見たことがあるんですが、それはとても綺麗な景色でした。
現在は、窒素肥料の普及と田植えの機械化などの理由で田植えの時期が早まったので、蓮華草が育つまで待ちきれずに「緑肥」を行うことが少なくなってきました。
蓮華草の名前の由来
こちらは、花の容姿にズームアップした名づけになっています。
紫雲英の花の様子が「蓮の花」の形に似ていることより「蓮華草」と名付けられました。
余談ですが、ラーメンを食べる時についてくるスプーンのような「レンゲ」も、同じ「蓮の花」の形に似ているから「レンゲ」と呼ばれるようになりました。
こうしてそれぞれの由来をまとめてみると
- 紫雲英:「その花々が群生している様子を遠巻きに観察してつけた名前」
- 蓮華草:「その花の特徴を間近で観察してつけた名前」
ということになりますね。
ひとつのことを調べていくと、いろんな方向に思いが巡ってとても面白いです。
【紫雲英】の素敵な花言葉たち

さて、だいぶんと紫雲英に詳しくなってきましたが、もうひとつ魅力的な情報があります。
花にはいろいろな花言葉がついています。
もちろん「紫雲英」にもちゃんと花言葉はあります。
どうせ路地や空き地に咲いている雑草でしょ?なんて、あなどってはいけませんよ。

とても素敵な花言葉なので、ぜひ覚えてくださいね♪
- 「感化」
- 「私の幸福」
- 「私の苦しみを和らげる」
- 「あなたと一緒なら苦痛が和らぐ」
- 「心が和らぐ」
とても癒しを感じる花言葉ですね。
素敵な花言葉が付けられた理由は2つある
優しい花言葉ばかりそろっている紫雲英の花言葉ですが、それにはこんな理由がありました。
「紫雲英」には薬効効果があるから
咳止めや喉の痛みなどの解毒作用や止血効果があります。
だから、こんなにも優しい花言葉がついているのですね。
「紫雲英」はギリシャ神話に登場しているから
花言葉はヨーロッパの文化の影響を色濃く受けて作られています。
もちろん、紫雲英の花言葉もその例外ではありません。

紫雲英の場合、ギリシャ神話が花言葉の由来になっています。
ここでは、そのエピソードをご紹介しますね。
【紫雲英にまつわるギリシャ神話のお話】
美しい二人の姉妹がおりました。
姉はドリュオペ、妹はイオレと言い、二人はとても美しかったそうです。
二人は祭壇にお供えするために花を摘みに出かけました。
野原に綺麗な紫雲英の花が咲いていたので、姉のドリュオペがそれを摘みました。
すると、摘んだ花の茎から赤い血がしたたり落ちてきたのです。
実は、この花はローティスという美しい妖精が、好色な神プリアポスから逃げ隠れるために姿を変えていたのでした。
それを知らずに摘み取ってしまったドリュオペは、足元から草に変わって行き、根が張り、どんどんとその姿は紫雲英の花になってしまいました。
最後の言葉としてドリュオペはイオレに言いました。
「これからはもう花を摘まないでね。すべての花は女神が姿を変えたものだから」
なんだかかわいそうなお話です……。
紫雲英の西洋の花言葉に、「your presence softens my pains(あなたと一緒なら苦痛が和らぐ)」というのがあります。
これは花と思って摘まれてしまったニンフが、ドリュオペを紫雲英の花に変えてしまうことで、その苦痛を和らげようとしたのでしょうか。
道連れにしたという事なんでしょうか…。うーん、ちょっと怖い気もしてきました……。

ちょっと邪推が過ぎたかもしれませんね。
紫雲英の花言葉には、不思議な魅力と癒しのパワーが込められているのだと感じました♪
「紫雲英」はこんな草花!
花の容姿のことに触れましたので、紫雲英の花の解説もここで詳しくしておきますね。
名称:紫雲英(ゲンゲ)
別名:蓮華草、蓮華(レンゲソウ、レンゲ)
学名:Astragalus sinicus
英名:Chinese milk vetch
分類:マメ科(ゲンゲ属)
原産地:中国
分類:越年草
草丈:10㎝~30㎝
開花時期:4月~5月
茎先に紫と白の色でグラデーションされた花びらが、蝶の形をしており、それが円を描くようにぐるりと輪を作ったような花の形をしています。

この形が蓮の花に似ているのですね!
地面を這うように広がって生え、葉は小葉が2列に整列したようになっている「羽状複葉」をしています。
ちなみに学名のAstragalusは、ギリシャ語で「くるぶし」という意味。
英名のChinese milk vetchは「この草を食べた羊はミルクの量が増える」といった意味があります。
紫雲英は雑草と思われがちですが、牧草としての役割もこなしているのですね。
また、ミツバチが好む紫雲英の花は、ハチミツを作るための「蜜源植物」として利用されているんですよ。
まとめ
- 紫雲英の読み方は「げんげ」
- 紫雲英の別名は「レンゲソウ」・「レンゲ」
- 紫雲英の花言葉は「感化」・「私の幸福」・「苦しみを和らげる」等
春うららかに日差し柔らかく、春の陽気ももうそこまで来ていますね。
この季節になると、ふと小学校の通学路の景色を思い出します。
道端や、田んぼの路地、空き地の隅っこなんかに咲いている紫雲英ですが、小さな花を咲かせるその姿はとても魅力的ですよね。
日当たりが良い場所に植えて、しっかりと水やりをすれば、鉢植えやプランターで比較的簡単に育てることが出来ます。
やや乾燥に弱いので水やりを忘れないようにすれば、病気になりにくいし害虫もあまりつかないので、ガーデニング初心者にはもってこいの花だと言えますね♪
でも、最近ではあまり見かけなくなって残念。
私と同じ世代の女の子はみんなだいたいレンゲソウを摘んで髪飾りを作ったものです。
しかし、今ではそんなことが出来るのはごく一部の地域だけになってしまったようです・・・・・・。

コメント