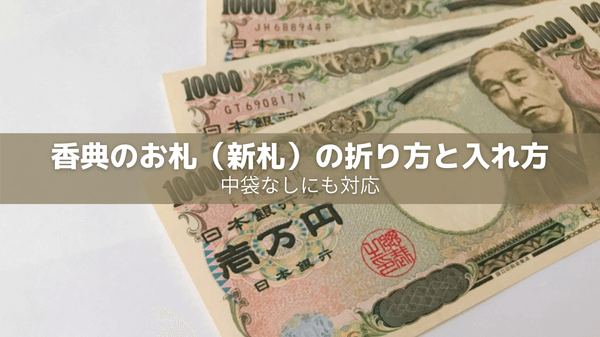
親戚や友人、知り合いの突然の訃報――。
通夜や葬式の支度でバタバタしている中、これでいいの?と疑問が湧くことがありませんか?

特に香典については、細かいルールがあるのでやっかい……。
一度疑問に思ってしまうと、気になって仕方ありませんよね?
そこで今回は
- 香典のお札(新札)の折り方
- 香典のお金の入れ方(中袋なし)
- お札の向きのルール
などを解説しましょう。
香典のお札(新札)の折り方
香典に新札を入れるのは縁起が悪いとされています。
そのため、新札をあたかも古いお札のように見せるため
お札を真ん中半分で軽く折る
こうした事前準備が必要です。
ただ、あまりに「くたびれて汚いお札」も失礼なので
- 何度も折ってクタクタにさせる
- 意図的に汚れをつける
といった行為はやり過ぎになるので注意しましょう。
香典のお金の入れ方(中袋なしに対応)

香典に入れるお札には正しい向きがあるんですよ。

お札の正しい向きは「裏向き」です。
お札の表・裏の判別の仕方は、1万円札であれば
- 福沢諭吉が印刷されている方が「表」
- 鳳凰(鳥)が描かれている方が「裏」
となります。
つまり香典袋に入れる際は、鳳凰(鳥)が描かれている方を表に向ければいいわけです。
このとき、お札の向きはそろえて、裏に顔が来るように、そして金額の数字を下から読む向きになるように入れます。
E
Y
0
0
0
0
1
このようにちょうどお札の左側を下にして入れる感じです。
ちなみに中袋の「ありなし」は関係ありません。

中袋があってもなくてもこの入れ方が共通となります。
香典を確認する時に気にする方も少ないので、お札の向きがそろっていれば、裏表どちらでもかまわないと言われています。
ただ、まだまだ年配の方も多いですので、香典は「裏」と覚えておく方がいいですね。
香典の表書きや渡し方の基本ルールはこちらの動画がくわしくですよ。
なぜ表は失礼で、裏にするのが正しいの?

では、どうしてお札は裏向きに入れるのでしょうか?
考えられる理由は3つありました。
1. 悲しみのために顔を伏せていることをあらわすため
2. 葬式では、亡くなった方の着物を左前にするなど、通常と逆のことをすることで非日常をあらわすからお札の向きも逆向きにする
3. 袋から出してすぐ数えられるよう、使う向きにお札を入れる
1つめは最近になって言われ始めたようです。
確かに覚えるためにこじつけたような感じがしますよね。

覚えやすくて便利ですけどね。
他の2つも、こうじゃないかという理由だけで、はっきりわからないんですよ。
庶民がお札を香典とするのは、昭和初期頃からなんですって。
歴史としては浅いのに、記録にはっきりと残ってないものなんですね。
香典の金額は中袋がない場合も書く?
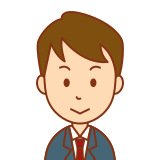
中袋のない香典の袋は、金額を書くと人目についてしまうので、なんとなくはばかられてしまいますが、書いていいのでしょうか?

はい、いいんです、金額は必ず書きましょう。
金額を書かないと、香典返しをする際に喪主が困ってしまいます。
確かに、金額がわからないと、
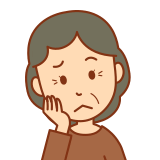
この人にいくら頂いたのかな。いくらのお返しをしたらいいの?
ってなっちゃいますよね。
喪主さんの手を煩わせないためにも、金額の他に住所もしっかりと記入しましょうね。
それでは書き方を説明しましょう。
中袋がない場合の金額の書き方
■裏側の水引より下の部分に薄墨で住所と金額を記入します。
■普通は縦書きで書きますので、金額は漢字を使います。
■漢字は改ざんを防ぐために「大字」を使います。
■香典では金額の最後に「也」はつけません。
- 金壱萬円
- 金弐万円
- 金参萬円
でOKです。
※香典の金額は偶数でも奇数でもかまいません。
まとめ
今でもそうですが、通夜や葬式は、久しぶりに会えた大勢の親戚や知人と、故人を偲びつつ食事をしますよね。
昔の香典は、この食事のための米や食材だったんですって。
お米といっても、米俵ですよ!
遠くの親戚だったら、持って行くのも一苦労ですね。
今はお金でよかった。
香典を渡すのが簡単になった分、マナーはしっかり覚えておきたいと思ったのでした。


コメント