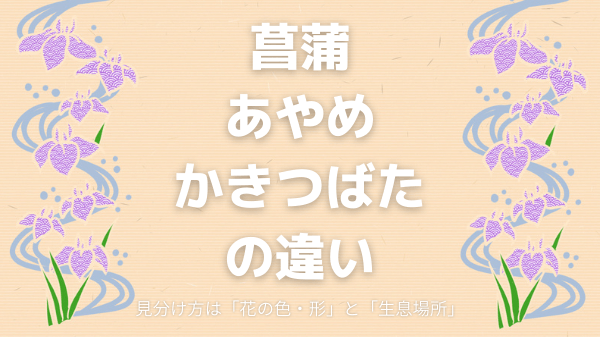
「いずれアヤメかカキツバタ」……この言葉は、どちらも優れていて優劣が付けづらいという意味があります。
「あやめ」と「かきつばた」が非常に似ていることからきているんですけど、それぞれの違い、わかりますか?
さらに漢字の菖蒲(しょうぶ)と平仮名のあやめの違いもご存知でしょうか?
近所の公園にすべての花が咲いているんですが、私の母に聞くと
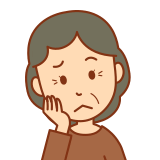
どれがどれだか、まったく区別がつかない!
っていうんですね……。
そこで、この記事では
- 菖蒲・あやめ・かきつばたの違い
- 簡単に見分けるポイント
- それぞれどんな花?

などなど花好きな私がご紹介します。
菖蒲・あやめ・かきつばたの違いと見分け方
菖蒲・あやめ・かきつばたは、「アヤメ科アヤメ属の多年草である」という点は同じです。

しかし、以下の2つの点で決定的な違いがあります。
- 花の色
- 生えている場所
「花」での見分け方
花で見分ける時は、外側の花びらを見てください。
- 菖蒲・・・花びらの中央に黄色い線が入っている
- あやめ・・・黄色に紫色の網目模様が花びらの付け根に入っている
- かきつばた・・・花びらの中央に白い線が入っている
菖蒲の花

菖蒲(花菖蒲ともいう)の花の特徴は、花びらの中央に黄色い線が入っている点です。
あやめの花

あやめの花の特徴は、複雑な網目模様が入っていること。
「あやめ」の名称の由来は、「あみめがあるから」という説もあります。
かきつばたの花

かきつばたの花の特徴は、白い線が入っていること。
他の2つの花に比べてシンプルな色合いなので、見分けがつきやすいかと思います。
「生えている場所」での見分け方
生えている場所でも明確な違いがあるので、カンタンに分かります。
- 菖蒲・・・水辺や湿地
- あやめ・・・水気のない乾燥したところ
- かきつばた・・・浅い水の中や湿地
菖蒲とかきつばたは水気のあるところ、あやめは完全に乾燥した場所という明確な違いがあります。
こちらの動画では3つの花の見分け方が分かりやすく解説されていますので、どうぞご視聴ください。
これでもう明日からばっちり見分けることができそうですね!
それでは、次にそれぞれの植物の由来や名所などを見ていきましょう。
菖蒲はどんな花?

菖蒲はどんな花なのでしょうか。
まず始めに知っておきたいのが、「菖蒲」という植物は2種類あるということ。
今回話題にするのは、きれいな花を咲かせるアヤメ科の方であることをお断りしておきますね。
もうひとつの種類は、菖蒲湯や菖蒲酒でおなじみのサトイモ科の多年草なんです。
そういうわけで、アヤメ科の菖蒲はサトイモ科の菖蒲と区別するために、「花菖蒲」とも呼ばれています。
花の見頃は6月頃です。

この花は、あやめやかきつばたよりも歴史は新しいんですよ。
江戸時代の旗本、松平左金吾がアヤメ科のノハナショウブを改良し、江戸ハナショウブを作り出したのです。
この江戸ハナショウブが肥後藩に伝わり改良されたのが肥後ハナショウブ、伊勢に伝わり改良されたのが伊勢ハナショウブと言われています。
現在、菖蒲はこの
- 「江戸ハナショウブ」
- 「肥後ハナショウブ」
- 「伊勢ハナショウブ」
の3つの系統にほぼ分かれるんですよ。
様々な観賞用品種があり、色も形も豊富であでやかで、あやめやかきつばたを押しのける勢いがあります。
今では「あやめ園」と言えばハナショウブの群生地を指すようになりました。
あやめの名所4選
日本四大あやめ園というのがあります。
- 新潟県の五十公野公園あやめ園
- 山形県の長井あやめ公園
- 茨城県の前川あやめ園
- 千葉県の水郷佐原あやめパーク
この4つを言いますが、名前を冠しているあやめよりも菖蒲の数が多く、菖蒲の名所なんですよ。
水郷佐原あやめパークの様子がよく分かる動画がこちら。
江戸時代から続く葛飾区の堀切菖蒲園や同じ葛飾区の水元公園もおすすめです。
あやめはどんな花?

次に、あやめはどんな花なのでしょうか。
あやめの名前の由来は
- 葉の模様や花びらに網目状の模様の文目(あやめ)から
- 輸入した漢部(あやべ)が転じてあやめとなった
- 青禰芽(あおいやめ)から転じたから
など諸説あります。
日本には昔からあったんですが、サトイモ科の菖蒲と一緒にされていたんですよ。
漢字で菖蒲と書いて「あやめ」と読むのは、昔の人もよく分かっていなかったからなんですね。
花の見頃は5月上旬~中旬で、青紫色の小ぶりの花がつきます。
菖蒲の名所でもある千葉県佐原市立水生植物園にも沢山植わっていますよ。
岡山県津山市の作楽神社は桜も有名ですが、あやめも有名です。
かきつばたはどんな花?

最後に、かきつばたはどんな花なのでしょう。
昔はかきつばたの「青紫色の花の汁」を染料にしていたんですよ。
そこから「書付花」と名付けられ、転じて「かきつばた」となったと言われています。
花の見頃は5月旬~下旬です。
かきつばたと言えば、在原業平『伊勢物語』の東下りが有名ですね。
という、かきつばたの歌が歌われたのが愛知県知立市八橋です。
ここにある八橋かきつばた園では「かきつばた祭り」も行われますよ。

京都の大田神社も有名です。
野生のかきつばたの群生が見られ、国の天然記念物に指定されています。
こちらも平安時代に藤原俊成が歌に詠んでいます。
現在は菖蒲の一人勝ち
こうして見ると、花の違いはいろいろあります。
人気度でいえば、江戸時代に品種改良された菖蒲が一番植わっている本数も多く、100万本を超えて栽培されているところもあるのでNO.1。
見分けが付かなかったら、とりあえず菖蒲じゃないかと考えてよいと思いますよ。
あやめやかきつばたも人気が出れば、いつか菖蒲を超えて栽培されるようになるかも知れませんね。
ちなみに私の家の近所に植えられているのも菖蒲でした。
まとめ
菖蒲・あやめ・かきつばたの違いは
- 花の色や形状
- 生えている場所
にあります。
違いに注目して観察していると、次第にひと目で判別がつくようになりますよ。
ぜひ美しいそれぞれの花を愛でて、違いの分かる人になってください。

コメント